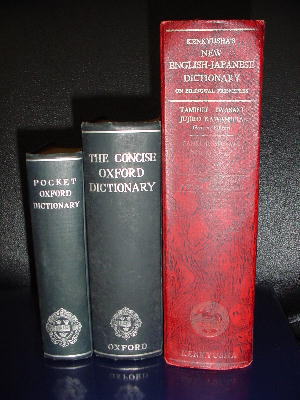

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�Q�O�D���C�t���[�N�Ƃ��Ă̎����ҏW
�͂��߂�
�@�����p��̎����ҏW�ɊW����悤�ɂȂ����̂́A1972�N�i���a47�N�j�̏t���A���������w�@��w���������Ă���ꂽ�S�i�i���j���j�搶����A�w���w�ك����_���n�E�X�p�a�厫�T�x�i�S4���G���́w���w��RHD�x�j�̍Z����������Ăق����ƈ˗����ꂽ������ł������B�搶�͓��������T�ҏW�ψ���̈ψ������Ă����A���͖@����w��C�u�t�ɂȂ�������ł������B�����T�͎��m�̂��Ƃ��A�A�����J�̑�^�p�ꎫ��The Random House Dictionary
of the English Language�\The Unabridged Edition�i����RHD�j��S�A�����̗p��E����������������̂ł������B�@����܂ŁARHD �ɂ��Ƃ��Ɗ܂܂�Ă������Ȃ���ʌ�T�����w�ٔł������p���ł��邱�Ƃ��S�i�搶�Ƃ̎G�k�̒��Ŏ��X�b��ɏ悹�Ă������Ƃ��v���o���Ă��������āA���w�ٔł̍Z������A�Ƃ�킯�q�A�r�̍����ŏ�����Ō�܂ŖȖ��ɖڂ�ʂ��A��A�͂������̂��ƁA�L�q�̌������������悤�Ȗ��E�p��E��������E�������Ăق����Ƃ����˗������������̂ł������B
�@���̎d���U�肪�]�����ꂽ�̂��Ǝv�����A���ꂩ��̎��͐��Ђ���ҏW��Ƃւ̗U�����A�����Ɏ����Ă���B���݂܂ł�40���N�A�p�ꎫ���Ɗւ���ė����킯�ł��邩��A���̕���ŗ������́A�܂��ɕ\��̂��Ƃ��u���C�t���[�N�Ƃ��Ă̎����ҏW�v�̓��ł������ƌ����Ă悢�ł��낤�B
�����ɋ�������������
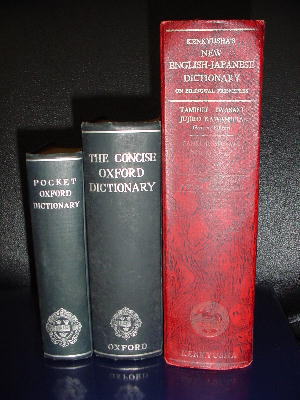

���ꂩ��40�N���N���o�߂���
�@�������̂ŁA�w���w��RHD�x�ɊW���Ă������40���N���o�߂����B�S�i�搶���炻�̎d���Ԃ��J�߂Ă����������̂��݂ɁA�w�����E�ׂ���l���w�\�ǂ����ǂ��Ⴄ�H�x(1977)�Ƒ肵���p�Č��r���T�A�w�Ԃ̉p��l���w�\�h���C�o�[�̉p��p�᎖�T�x�i1977�j�Ƒ肵�����ꎫ�T�A�@�w�A�����J��@���T�x�i1983�G�h�C�c�ꂩ��̕��S�|��j�Ƒ肵����@���T�A�w���w�ىp�a�ŐV�ꎫ�T�x(1981)�A�w�p��Ȃ��V�ю��T�x�i�S�i���j���G1982�G�����L���ƕ����֘A�̋L�q��S���j�A�w���w�ٍŐV�p���T�x�i1983�G���ɃC�M���X�֘A�ꂨ��ю����Ԋ֘A������M�j�A�w�w���J���[�A���J�[�p��厖�T�x(1984�G���ɃC�M���X�֘A���ڂ����M)�A�@�w�����Ѓ��[�_�[�Y�v���X�x(1984�G�V��ƃC�M���X�֘A������M)�A�w�Č�ΏƁE�C�M���X����w�K���T�x(1991)���X�Ɍ��e������A�|��E�ҏW�����肵�Ď������ɋ��͂����B
�ҏW�劲�Ƃ���

�����ƂƂ��Đh����������
�@�����ƂƂ��Ă̎����S�g�S����w�m�`�a�p�x�̕Ҏ[��Ƃɖv�����Ă���1989�`90�N�̍��A�����^�R�C���Ŏ��̎��Â��邽�߂ɋߏ��̎��Ȉ�Ɏ����ܒʂ��Ă����̂����A���s�������Ȃ����������̐��𑝂��čs�����B�w�r�`�p�a�x�̕ҏW��ƂɎ��|���������A1995�N�i�����V�N�j�̏��Ă̍����Ǝv�����A�Ƃ��Ƃ����̎��s�ُ͈�ȂقǃK�^�K�^�ɂȂ��Ă��܂����B�����̐�����3���ԑO��ł������B�^���s���̂��߂ɐH�ׂ������������ꂸ�ɓ��A�a�ɂȂ������ƂɌ������������B���̌��ʁA���ꂪ�������s�ɉe�����y�ڂ��A����āA��������13�{�����������Ă��܂����B���m�Ɍ����A�u�����������v�̂ł͂Ȃ��A�����Łu����������v�̂��B�S�Ă̎����O���O�����ċC�������������߁A1�{1�{�����̎�ň��������Ĕ����čs���̂��B�c���Ă����킸��3�{�̎���S�Ď����Ŕ���������̂́A�Y������Ȃ�1999�N�i����11�N�j�̉Ă������B���ʓI�ɁA55�̒a�����܂ł��ƂЂƌ��Ƃ������ɁA���O�̎���1�{���c���Ă��Ȃ��Ƃ���"�S��(����)����L��l"�ł������i�u�W�X(����)����L��l�v�ł͂Ȃ��I�j�B
�@����Ȓ��A40�N�߂��A��Y�����A�܂��ɑ��f�i���������j�̍Ȃ������X�����Ɛf�f���ꂽ�B2008�N�i����20�N�j5��2���̂��Ƃł������B�]�����N�Ɛ鍐���ꂽ�Ȃ́A���ʓI�ɂ͂��ꂩ��1�N4���������B�䂪�q�����ƃn���C���s�ɂ��A���������������s�ɂ��s�����B���̂悤�ȕn�R�w�҂ƌ����������߂ɁA40�N�߂��A���܂肢���v�������邱�Ƃ̂Ȃ������ȂɁA���͘l�т閈�������A�����ҏW�劲�Ƃ��Ă̎d���͌l�I�����������Ă���Ȃ��B
�@���͎�`�Ƃ��āA�����̊j�ɂȂ镔���͎����Ŏ��M���Ȃ���C���ς܂Ȃ��̂����A���ꂪ��̓I�ɂ͂ǂ��������Ƃ�����낤�ɂ��A�������ʂ��Ȃ��B�@������߂āA�����ƂƂ��Ă̎��̐l���ɂ��ďڂ��������Ă��������B��ɑ����Ⴂ�l�����ɂ����Ɩ𗧂��낤�Ǝv������ł���B
�y���L�z�{�L���́u�p�ꋳ��v���i2014�N 3�����A��C�ُ��X�j�Ɋ�e�������͂ł��i�ꕔ�̎���̕\�L���C�����܂����j�B